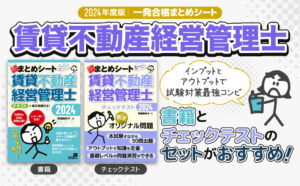今日は、平成28年度 第30問について解説します。
建物の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 特殊建築物等の所有者又は管理者は、定期に、一級建築士等に調査をさせなければならない。
② 予防保全は、事故や不具合が生じる前に、あらかじめ適切な処置を施す保全である。
③ 事後保全は、事故や不具合が生じてから、修繕等を行う保全である。
④ 予防保全においても、事後保全においても、法定耐用年数どおりに機器を交換することが重要である。
解説
建物の維持保全に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
特殊建築物等の所有者又は管理者は、定期に、一級建築士等に調査をさせなければならない。
〇適切です。
建築基準法第12条では、政令および特定行政庁が指定する、建築設備、防火設備、等の所有者・管理者は、定期的に敷地、構造、建築設備の維持管理状況を有資格者に調査・検査させて、その結果をに報告することが義務付けられています。
なお、この有資格者には、一級建築士、二級建築士、その他の調査員・検査員が含まれます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
予防保全は、事故や不具合が生じる前に、あらかじめ適切な処置を施す保全である。
〇適切です。
予防保全とは、点検や保守によって前兆をとらえ、建物や設備が故障する前に適切な処置を行うものです。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
事後保全は、事故や不具合が生じてから、修繕等を行う保全である。
〇適切です。
選択肢の説明の通り、事後保全は、事故や不具合が生じてから、修繕等を行う保全ですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
予防保全においても、事後保全においても、法定耐用年数どおりに機器を交換することが重要である。
×不適切です。
法定耐用年数とは、法令で定められた資産価値が消滅するまでの期間のことであり、実際の設備や建物の寿命とは一致しない場合があります。
予防保全では、法定耐用年数にとらわれず、劣化状況や収支を考慮しながら、予防的に交換・保守・修繕することが求められます。
なお事後保全は事故や不具合が発生してから修繕を行いますので、法定耐用年数どおりではなく、設備の状態で判断するものと考えられます。
つまり、予防保全においては、法定耐用年数にとらわれず、劣化状況や収支を考慮しながら、予防的に交換・保守・修繕することが重要です。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。
★関連解説★
2024年度版 一発合格まとめシート
2025年版は準備中です