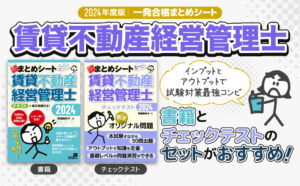今日は、令和6年度 第32問について解説します。
賃貸住宅管理業法の不当な勧誘等の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当する。
② 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を解除しようとしている賃貸人に対し、契約期間中の解除はいかなる場合も認められないと説明し解除を断念するよう説得したが、それでも賃貸人が解除の意思表示をした場合には、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
③ 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否したにすぎないときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
④ 特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した際に行われた場合であっても、禁止される不当な勧誘等に該当する。
解説
不当な勧誘等の禁止に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当する。
×不適切です
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結するために相手方(貸主)の判断に影響を及ぼす重要なものについて故意に告げないこと(事実不告知)は禁止されています。
相手方の判断に影響を及ぼす重要なものとは、相手方の不利益に直結するもののことを指します。
特定賃貸借契約の場合、転貸人(特定転貸事業者)が貸主に家賃を支払いますので、転貸人が転借人から受け取る家賃の管理については、貸主に直接関係する事項ではありませんので、告げなくても貸主の不利益に直結することはないと言えます。
つまり、特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当しません。よってこの選択肢は不適切です。
なお、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものは、次の事項が挙げられます。
・特定転貸事業者が特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額等の賃貸の条件やその変更に関する事項
・特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の内容及び実施方法
・契約期間に発生する維持保全、長期修繕等の費用負担に関する事項
・契約の更新又は解除に関する事項
特定賃貸借契約の重要事項説明の内容と似ていますね。
選択肢 ②
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を解除しようとしている賃貸人に対し、契約期間中の解除はいかなる場合も認められないと説明し解除を断念するよう説得したが、それでも賃貸人が解除の意思表示をした場合には、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
×不適切です
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の解除を妨げために相手方(貸主)の判断に影響を及ぼす重要なものについて、故意に不実のことを告げる(不実告知)ことは禁止されています。
期間内解除条項がある場合、正当事由を具備することにより、特定賃貸借契約の契約期間中であっても貸主からの契約解除の申し入れが有効になる場合があります。
また、特定転貸事業者が特定賃貸借契約上の義務に違反したことによって貸主からの解除が認められる場合も考えられます。
したがって、いかなる場合も契約期間中の解除は認められないという説明は、事実とは異なるものであり、不実告知に該当します。
さらに、不実告知の事実があれば不当な勧誘等に該当し、実際に契約解除が妨げられたか否かは問いません。
つまり、特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を解除しようとしている賃貸人に対し、契約期間中の解除はいかなる場合も認められないと説明し解除を断念するよう説得したが、それでも賃貸人が解除の意思表示をした場合には、禁止される不当な勧誘等は該当します。よってこの選択肢は不適切です。
なお、この事実と異なった説明が故意(事実ではないと知りながら)かどうかは明記されていませんが、特定転貸事業者であれば当然に事実ではないことと知っていると思われる事項については故意だとみなされる場合があります。
ですので、不当な勧誘等に該当する要件を満たしていると言えます。
選択肢 ③
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否したにすぎないときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
×不適切です
特定賃貸借契約の相手方の保護に欠けるものとして、契約の締結をしない旨の意思を表示した相手方等に対して執ように勧誘する行為は、不当な勧誘等に該当します。
相手は自宅への訪問を拒否したのではなく、勧誘行為自体を拒否していますので、電話で勧誘するなど手段を変えたとしても、迷惑だと断ったのにも関わらず執ような勧誘をしていると言えます。
つまり、特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否しているときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等に該当します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した際に行われた場合であっても、禁止される不当な勧誘等に該当する。
〇適切です。
相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為は、不当な勧誘等に該当します。
迷惑を覚えさせるような時間というのは、一般的には午後9時から午前8時までの時間帯をいいます。
この場合は、その時間に相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問していますので、相手方にとっては迷惑な時間帯ではない可能性があります。つまり、時間帯的には不当な勧誘等に該当するものではないとも考えられます。
ただし、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、不当な勧誘等に該当します。
選択肢の説明の通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。
選択肢の言葉を分解していくと一つ一つはそこまで難易度が高いものではなくても、組み合わさることで混乱することがあります。
令和6年度試験は、このような問題が散見されます。
令和7年度以降の試験も同様の傾向となる可能性がありますので、ミスリードに惑わされないようしっかりと基本事項をおさえて学習を進める必要があります。
ぜひ過去問解説については、適切か不適切かを確認するだけではなく、「どこの部分がどのように不適切(適切)か」を理解していただき、得点アップにつなげていただければと思います。
2024年度版 一発合格まとめシート
2025年版は準備中です