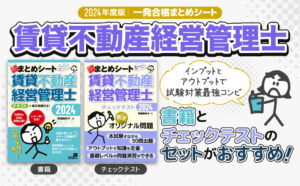今日は、令和6年度 第23問について解説します。
建物賃貸借契約と破産に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 賃借人につき破産手続が開始すると、賃貸借契約は終了する。
② 賃借人につき破産手続が開始すると、開始決定までに生じた未払賃料債権は破産債権として扱われ、破産手続によらない限り、破産管財人から弁済を受けることができない。
③ 賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は敷金返還請求権を行使することができない。
④ 賃貸人につき破産手続が開始すると、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することができない。
解説
建物賃貸借契約と破産に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
賃借人につき破産手続が開始すると、賃貸借契約は終了する。
×不適切です
民法上では、借主の破産そのものは賃貸借契約の解除理由にはならず、破産手続の開始だけで賃貸借契約が当然に終了するわけではありません。
破産は借主個人の財政状態に関する問題であり、賃貸借契約自体の債務不履行には該当しないためです。
つまり、賃借人につき破産手続が開始しても、賃貸借契約は当然に終了することはありません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
賃借人につき破産手続が開始すると、開始決定までに生じた未払賃料債権は破産債権として扱われ、破産手続によらない限り、破産管財人から弁済を受けることができない。
〇適切です。
破産手続が開始されると、それまでの未払賃料は破産債権となり、破産手続を通じて配当を受ける形になります。
破産手続を経ずに破産管財人から直接支払いを受けることはできません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
なお、貸主の賃料債権は、破産手続開始決定前に生じたものは破産債権として扱われ、破産手続を通じて弁済を受けることになります。
一方、破産手続開始後に発生する賃料債権は、財団債権として扱われ、破産財団から随時弁済を受け取ることができます。
選択肢 ③
賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は敷金返還請求権を行使することができない。
〇適切です。
破産手続の開始が決定されると、破産者は財産に関する管理処分権を失います。
破産者の財産は、破産財団となり、破産管財人が管理処分権を持つことになります。
敷金返還請求権は破産者の財産のひとつであるため、破産財団に属することになります。
選択肢の説明の通り、賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は自ら敷金返還請求権を行使することができませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
賃貸人につき破産手続が開始すると、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することができない。
〇適切です。
賃貸借契約は双務契約といって、契約する双方がお互いに債務を負担する契約です。
貸主は物件を使用収益させること、借主は賃料を支払うことなどが、それぞれの債務(果たさなければいけない義務)ですね。
双務契約において、当事者双方が債務を履行していない場合には、破産管財人は契約の解除または履行のいずれかを選択することができるとされています。
ただし、借主が賃貸住宅の引渡しを受けている(賃借権の対抗要件を備えている)場合には、解除権を行使することはできません。
借主が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、選択肢の説明の通り、貸主の破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することはできませんのでこの選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
本問は、選択肢②、④は特に難しく感じるかもしれません。
選択肢①については、この論点において比較的基本的な知識なので、ぜひ判断ができるようにしていただきたいです。
①が誤りだと自信を持って答えられれば、仮に選択肢②~④が分からなくても正解でき、1点を確実に獲得できます。
これから試験に挑戦する方にとっては、とにかく浅く広くたくさんのことを覚えるよりも、基本的な知識を確実に理解することが重要です。
一緒に頑張りましょう!
ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
★関連解説★
2024年度版 一発合格まとめシート
2025年版は準備中です