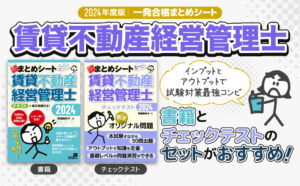今日は、令和6年度 第17問について解説します。
月額賃料10万円の賃貸住宅につき、賃借人が月額賃料7万円への減額を請求した場合に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
① 敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。
② 賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。
③ 賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。
④ 賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。
解説
賃料の減額請求に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。
×不適切です
敷金契約は、賃貸借契約とは別個の契約ですので、賃料減額請求権を行使したからといって敷金も自動的に減額されることはありません。
つまり、敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も連動して減額になる制度はありませんので、賃貸人は敷金の差額分を返還する義務はありません。よってこの選択肢は不適切です。
なお、敷金については増減額請求をすることはできないとされています。
選択肢 ②
賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。
〇適切です。
賃料増減額請求は、賃料増減請求権を行使するまでの事情に基づいて判断されます。
賃料増減請求権を行使した後、さらに増減請求が必要な事情が発生した場合でも、既に行使した賃料減額請求の判断には影響しません。
選択肢の説明の通り、賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはなりませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。
〇適切です。
賃料増減請求は、相手に通知することによってその権利が行使されます。
借主が減額請求をする場合には、貸主に対して賃料減額を通知することによって、賃料減額請求権を行使したものと認められます。
また、法律上は、書面が必要とされるものではなく、口頭での請求も認められます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。
〇適切です。
借主が賃料の減額を請求したものの、貸主がこれを拒み合意に至らない場合には、まず調停の申し立てを行います(調停前置主義)。調停でも解決しない場合には、裁判所の判断を求めることとなります。
この場合、裁判が確定するまでの間、貸主は相当と求める額の賃料の支払いを請求することが可能です。
裁判が確定するまでの間に受領した賃料に過払があった場合、貸主は受け取った賃料の過払額を返還する必要があり、その場合年1割の割合による利息を付加しなければならないとされています。
逆に、受領した賃料に不足があった場合には、貸主は借主に対して法定利率を付して請求することが可能です。
借主が、裁判が確定するまでに支払っていた賃料は1万円不足しますので、選択肢の説明の通り、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができますので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
★関連解説★
2024年度版 一発合格まとめシート
2025年版は準備中です